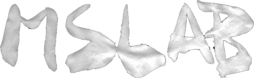正月恒例『mslabの干支の料理』!2002年午年は、タルタルステーキに挑戦です。 八世紀に現れた蒙古系部族・韃靼人(ダッタン人=タタール人)がヨーロッパに伝えたとされる料理で、生の馬肉を細かく叩き、玉葱などのみじん切り…
2001年-巳年『イラブーシンジ』
巳年である!21世紀である! …とまぁ、いろいろ考えた末、2001年の年賀状は“イラブー”です。 猛毒を持つ沖縄のウミヘビ。那覇の国際市場に行けば、とぐろ状、棒状の薫製が売られています。 さて料理法は… の前に、まず、こ…
2000年-辰年『伊勢エビの炒めもの広東風』
さて、20世紀最後の年、2000年は辰年です。 福井県辺りで発掘された恐竜の骨を出汁にして、コモドオオトカゲでも煮込み、ズズイと吸えば、貴方のDNAに微かに残る、本物の『竜』のイメージが蘇るかも… でもそれは、千年どころ…
1999年-卯年『バレンシア風パエリア』
mslab恒例の「干支のお料理」、1999年は卯年ということで動物愛護系の方からは眉をひそめられそうな料理にならざるを得ません。一時は“リンゴの兎”も考えたのですが、これまたグルメ系から「手抜きだ!」と批判を浴びそうです…
1998年-寅年 『虎魚(オコゼ)の造り』
1998年、mslab新年恒例の「干支の料理」は? 寅年とはいえ、虎のステーキてなわけにはいきません。ワシントン条約でお縄になるのは御免ですから。 漢方では「虎の陰茎を干したもの」という恐ろしげな食材(薬剤?)もあるそう…
1997年-丑年『牛肉のビール煮』
1997年、mslab恒例の干支のお料理は“牛肉のビール煮”だ(96年のネズミに比べれば軽い軽い!?)。 コツは、良いビールを使うこと。苦いばかりの日本のビールでは美味しく出来ない。ベルギーのトラピストタイプ(伝統的な手…
1996年-子年『活き海老のプリッキヌーソース』
1996年は鼠年だ。mslab恒例の干支の料理による年賀状は、大きな試練の年を迎えた。戌年をホットドッグで誤魔化してヒンシュクを買ったことが数年前にあるだけに、半端なことは出来ない。意地の悪い友人たちは前の年の夏頃から「…
1995年-亥年『猪肉のステーキ・マッシュルームソース』
1995年猪年、mslabの年賀状を飾った料理。 数年前より続いていた干支の料理による年賀状だが、猪は結構困ったものの一つだ。まず、材料が手に入らない。猪肉は、山梨や宮崎で食べたこともあるし、宮崎の出身の友人からは、皮付…