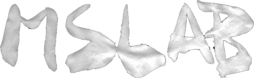Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2025! 2025年、新年のご挨拶はトルコ語です。 30回目を迎えた、『MSLABの干支のお料理』。難関の巳年(へび年)です。 2001年は、沖縄の海蛇(イラブー)を使…
カテゴリー: 06 巳年(Snake)
2013年-巳年『ワイルドストロベリーのスコーン』
19回目の「mslab 干支のお料理」をお届けします。 2013年は難関の巳年。12年前は沖縄の海蛇=イラブーで乗りきりましたが、他に蛇がらみの料理や食材はあるのか? ふと思いついたのが「ヘビイチゴ」。40代・50代以上…
2001年-巳年『イラブーシンジ』
巳年である!21世紀である! …とまぁ、いろいろ考えた末、2001年の年賀状は“イラブー”です。 猛毒を持つ沖縄のウミヘビ。那覇の国際市場に行けば、とぐろ状、棒状の薫製が売られています。 さて料理法は… の前に、まず、こ…