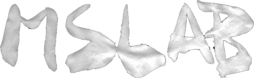MSLAB恒例の干支のお料理、辰年は毎回悩ましいのですが、2024年は太刀魚の韓国風スープ『カルチクッ』にしました。 なぜ太刀魚? 釣り人たちの間では、大きな太刀魚を“ドラゴン”と呼ぶのです! そう言われてみれば、龍宮城…
カテゴリー: 05 辰年(Dragon)
2012年-辰年『龍井蝦仁』
2011年が良い年だったと言える人は少ないのではないでしょうか。 学生時代に、曲がりなりにも原子物理学をかじった経験のある私にとって、福島第1の事故は、まさに痛恨。原子力の怖さは知っていたし、いつかは大事故が起きるだろう…
2000年-辰年『伊勢エビの炒めもの広東風』
さて、20世紀最後の年、2000年は辰年です。 福井県辺りで発掘された恐竜の骨を出汁にして、コモドオオトカゲでも煮込み、ズズイと吸えば、貴方のDNAに微かに残る、本物の『竜』のイメージが蘇るかも… でもそれは、千年どころ…