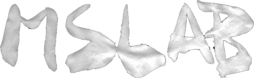やってきた卯年。フランス料理のレシピから兎肉の料理をご紹介します。 Lapin a l’andersen(兎のビール煮アンデルセン風)。 ご存じの通りアンデルセンはデンマークの童話作家。フランス語の料理名に“…
カテゴリー: 04 卯年(Rabbit)
2011年-卯年『兎肉の網焼き』
Bonne Annee ! フランス語の新年の挨拶で始まる今年は卯年。 うさぎ肉は、最近の日本ではポピュラーな食材ではありませんが、一昔前までは、どこの田舎でも日常的に食べられていた貴重なタンパク源です。今日でも、フラン…
1999年-卯年『バレンシア風パエリア』
mslab恒例の「干支のお料理」、1999年は卯年ということで動物愛護系の方からは眉をひそめられそうな料理にならざるを得ません。一時は“リンゴの兎”も考えたのですが、これまたグルメ系から「手抜きだ!」と批判を浴びそうです…