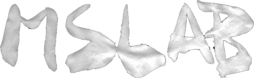Gambas al Pil Pil なにやらオミクロンな状況で迎えた2022年…と意味不明なフレーズから始めたくもなります。コロナ禍2度目の新年となってしまいました。 2022年は寅年。MSLABの干支の料理にとっては最…
カテゴリー: 03 寅年(Tiger)
2010年-寅年『虎豆煮』
2010年は寅年。一回り前は「虎魚(オコゼ)の造り」でなんとかクリアしましたが、果たして、他に虎がらみの食材や料理はあるのか… かなりの難関でしたが、ありました! 「虎豆」です。さっそく、北海道産のものを仕入れました。 …
1998年-寅年 『虎魚(オコゼ)の造り』
1998年、mslab新年恒例の「干支の料理」は? 寅年とはいえ、虎のステーキてなわけにはいきません。ワシントン条約でお縄になるのは御免ですから。 漢方では「虎の陰茎を干したもの」という恐ろしげな食材(薬剤?)もあるそう…