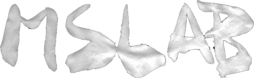2020年は子年。3周目に入ったMSLABの干支の料理ですが、またまた難関を迎えました。 ウェブや文献などいろいろ調べて、たどり着いたのが、「ネズミモチ」。街路樹として植えられることもあります。 そう言えば、どこかの公園…
カテゴリー: 01 子年(Rat)
2008年-子年『海鼠の海鼠腸和え』
「mslabの干支のお料理」も二周目。2008年は最大の難関と思われる子年を迎えました。十二年前は「ネズミの糞」という名を持つタイの激辛唐辛子で乗りきりましたが、他に「ねずみ」に関連する料理や食材は… ありました!ナマコ…
1996年-子年『活き海老のプリッキヌーソース』
1996年は鼠年だ。mslab恒例の干支の料理による年賀状は、大きな試練の年を迎えた。戌年をホットドッグで誤魔化してヒンシュクを買ったことが数年前にあるだけに、半端なことは出来ない。意地の悪い友人たちは前の年の夏頃から「…