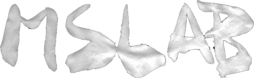mslab恒例の”干支のお料理”。20年目の2014年、午年を迎えました。 馬肉料理と言えば熊本の馬刺しに江戸の桜鍋と国内にもいろいろありますが、日本列島だけではありません。旧モンゴロイド系の遊牧…
投稿者: mslab
2013年-巳年『ワイルドストロベリーのスコーン』
19回目の「mslab 干支のお料理」をお届けします。 2013年は難関の巳年。12年前は沖縄の海蛇=イラブーで乗りきりましたが、他に蛇がらみの料理や食材はあるのか? ふと思いついたのが「ヘビイチゴ」。40代・50代以上…
2012年-辰年『龍井蝦仁』
2011年が良い年だったと言える人は少ないのではないでしょうか。 学生時代に、曲がりなりにも原子物理学をかじった経験のある私にとって、福島第1の事故は、まさに痛恨。原子力の怖さは知っていたし、いつかは大事故が起きるだろう…
2011年-卯年『兎肉の網焼き』
Bonne Annee ! フランス語の新年の挨拶で始まる今年は卯年。 うさぎ肉は、最近の日本ではポピュラーな食材ではありませんが、一昔前までは、どこの田舎でも日常的に食べられていた貴重なタンパク源です。今日でも、フラン…
2010年-寅年『虎豆煮』
2010年は寅年。一回り前は「虎魚(オコゼ)の造り」でなんとかクリアしましたが、果たして、他に虎がらみの食材や料理はあるのか… かなりの難関でしたが、ありました! 「虎豆」です。さっそく、北海道産のものを仕入れました。 …
2009年-丑年『ヤムヌア』
2009年は丑年です。「干支のお料理」としては楽勝コース!なのですが、いざ、どこの国のどんな料理にしようかと考え出すときりがなくなってしまいます。 さて、世相を見れば、あいかわらず世界各地で戦火が絶えず、守銭奴たちのマネ…
2008年-子年『海鼠の海鼠腸和え』
「mslabの干支のお料理」も二周目。2008年は最大の難関と思われる子年を迎えました。十二年前は「ネズミの糞」という名を持つタイの激辛唐辛子で乗りきりましたが、他に「ねずみ」に関連する料理や食材は… ありました!ナマコ…
2007年-亥年『猪肉の炭火焼き』
2007年は亥年。 世の中あまり良いことのなかった去年から、今年は猪が時代を切り拓いてくれるのか… 否、猪が何かをしてくれるわけではありません。しかし、ためらうことなく一歩を踏み出す猪の姿からは、少しばかり学ぶところがあ…
2006年-戌年『狗不理包子』
2006年は戌年。難関である。 実は、『MSLABの干支のお料理』は2005年の酉年から二巡目に入っています(最初の二年は、もろもろデジタル化が進んでいなかったため記録が残っていない)。1994年の戌年は、ホットドッグで…
2005年-酉年『参鶏湯』
2005年は酉年。女たちの韓流ブーム、男たちの北朝鮮バッシングというあまりに捻れた日本海の東と西にも新年はやってきます。mslab恒例の『干支のお料理』は参鶏湯。これしかない! 小さめの丸鶏に、餅米、高麗人参、乾燥棗(な…
2004年-申年『XO醤炒猴頭菇』
猿料理といえばインディジョーンズ!という話もありましたが、さすがに猿の活 け作りは厳しいものがあります。これはかなり苦しい… しかし!真面目に取り組んでみたらあったんですね。申年料理が。 栄えある申年料理の食材として選ば…
2003年-未年『クスクス』
mslab 恒例の『干支のお料理』、2003年はマグレブ(maghreb=北西アフリカのモ ロッコ、アルジェリア、チュニジアの三国を指す)からリビアにかけての代表的 料理、クスクス(couscous)です。マグレブの旧宗…