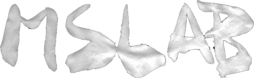mslabの干支の料理は32回目。3巡目も中盤にさしかかっています。 午年。2002年は『タルタルステーキ』、2014年は『馬肉のロースト』でした。 満を持して!というわけでもありませんが、2026年は、馬肉料理の王道と…
投稿者: mslab
2025年-巳年『坊さんの気絶(トルコ風ヘビナスの詰め物)』
Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2025! 2025年、新年のご挨拶はトルコ語です。 30回目を迎えた、『MSLABの干支のお料理』。難関の巳年(へび年)です。 2001年は、沖縄の海蛇(イラブー)を使…
2024年-辰年『カルチクッ(太刀魚の韓国風スープ)』
MSLAB恒例の干支のお料理、辰年は毎回悩ましいのですが、2024年は太刀魚の韓国風スープ『カルチクッ』にしました。 なぜ太刀魚? 釣り人たちの間では、大きな太刀魚を“ドラゴン”と呼ぶのです! そう言われてみれば、龍宮城…
2023年-卯年『兎のビール煮アンデルセン風』
やってきた卯年。フランス料理のレシピから兎肉の料理をご紹介します。 Lapin a l’andersen(兎のビール煮アンデルセン風)。 ご存じの通りアンデルセンはデンマークの童話作家。フランス語の料理名に“…
2022年-寅年『シータイガーのピルピル』
Gambas al Pil Pil なにやらオミクロンな状況で迎えた2022年…と意味不明なフレーズから始めたくもなります。コロナ禍2度目の新年となってしまいました。 2022年は寅年。MSLABの干支の料理にとっては最…
2021年-丑年『ハンギ(マオリ風牛肉と野菜のロースト)』
世の中大混乱の2020年を引きづったまま2021年へ。 恒例の「MSLABの干支の料理」は丑年を迎えました。 生産時の環境負荷が高い牛肉は、このところ逆風にさらされています。 今後は牛肉の消費量が減っていくのか… 環境負…
2020年-子年『女貞子鶏湯(ねずみもちの薬膳スープ)』
2020年は子年。3周目に入ったMSLABの干支の料理ですが、またまた難関を迎えました。 ウェブや文献などいろいろ調べて、たどり着いたのが、「ネズミモチ」。街路樹として植えられることもあります。 そう言えば、どこかの公園…
2019年-亥年『猪鍋』
「勝手に恒例(笑)」となっている<MSLAB 干支の料理>。2019年は猪年です。 過去を振り返ると、1995年はちょっと気取って「猪肉のステーキ・マッシュルームソース」、2007年はワイルドに「猪肉の炭火焼き」でした。…
2018年-戌年『小豆飯』
2018年、戌年の幕が開きました。 MSLABの『干支の料理』は、イヌの祖先、狼に奉げます。 『小豆飯(あずきめし)』です。 狼を神として崇める複数の神社(三峯神社・宝登山神社など)で神饌として使われます。 なぜ、狼が神…
2017年-酉年『タイ風焼き鳥 Gai Yaang』
2017年、酉年がやって来ました! mslab恒例の“干支の料理”は楽勝! 世界中に鶏料理はあまたありますから。 しかし、あまたある故、その中から何を選ぶか… “干支の料理”、Web上では22年目ですが、年賀状としては2…
2016年-申年『猿梨のフルーツサラダ』
来てしまった… 申年が! 『mslabの干支のお料理』にとっての最難関です。 12年前は、「ヤマブシタケ=猴頭菇(=テナガザルの頭のような茸)」で乗りきりました。 さぁ、2016年は? 『猿梨』の登場です! マタタビ科マ…
2015年-未年『ギリシャ風野菜の羊挽肉詰(Yamista)』
明けましておめでとうございます。 2015年の幕開け!未年ですね。 MSLAB恒例の”干支の料理”は2度目の羊料理です。 羊は世界中で様々な食べられ方をしているので楽勝!と思いきや、いろいろありす…